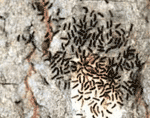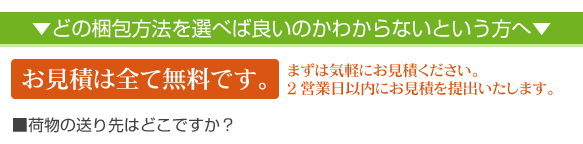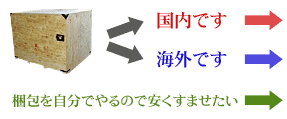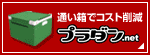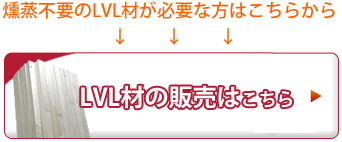どうして神戸港までが?
本日付の「海事プレス」紙16 ページに「神戸港、樹木剪定や薬剤散布強化へマイマイ蛾対応、今年
50 数港で採集調査北米防疫機関、貨物規制でシステム開発要求」 との見出しでほぼ1 ページの記事が掲載されています。ある程度経緯を知っている方は、「どうして神戸港までが?」と不思議に思うでしょう。
2007年6月からアジア地域に生息するマイマイガ(AGM Asian Gypsy Moth)の侵入を防ぐため、北米三国検疫機関(NAPPO)では、日本の特定港湾に夏場の産卵期に寄港する船舶の害虫不在証明検査を要求しました。指定港は大分、広島、阪南、酒田、八戸、函館の6港でした。(指定解除には二年連続で基準を下回る必要がある)指定港を通って米加両国に入港する船は、マイマイガの活動期の数カ月間、検査機関によるAGM
の「不在証明書」を取得するか、現地で沖合検査を義務付けられます。
ところが昨年7月にシアトルに入港した”Singapore Express”号に積んだコンテナの下部側面からAGMの卵塊が発見されたりしています。この船の最終港が神戸であったようです。
西岸・ガルフの港で、指定港以外からほかの船舶にも船体・コンテナなどに卵塊などが頻繁に検出されているため、NAPPO側は「完全にAGM
が生息しないことを宣言した港以外は全て検査対象とする」ルールをAGM規制の第二次案として要求して来たのですが、2月上旬に米国、カナダ、日本の3カ国が協議し、マイマイガ捕獲調査結果から苫小牧・小樽・清水・神戸の4
港の追加指定が3月末に確定したものです。 |
貨物検査について
NAPPO(米国・カナダ当局)では、厳しい規制を日本・韓国・中国に要求すべく、さる2月にAGM規制の第二次案と共に各国を歴訪しました。東京では2
月4 日にNAPPO/農水省植物防疫課の説明会があり日本荷主協会も出席しました。そこで明らかになったことは、貨物検査についてはNAPPO
側が具体的な規則を作るのではなく、それぞれの関係国検疫機関が自主的に検査基準を作るようにとの方向です。貨物検査の合格証は、輸入通関書類として提出させようと考えているようです。
NAPPO 側では在来船貨物や梱包なしに船舶に積み込む重機・車両、自動車そしてコンテナの外部を検査対象に要求したい模様です。コンテナの中に積み込む梱包や梱包の中身にまで目視検査を要求しているものではないようです。しかし、日本の農水省の決める検査基準がどのようになるかはまだ何も分かりません。貿易業界や梱包業界にとり過剰な検査基準にならぬよう、注目する必要があるでしょう。
(関連情報はISPM Report No.08-11 08年9月3 日、No.08-14 08年10月31 日を参照ください。) |
| 文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp |